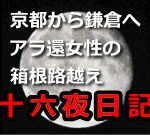2025年(R7)4月19日(土)2名
しょっぱなからつまづく!
昨年(2024年)11月に山北つぶらの公園に行って、ツツジの咲く4月ごろにもう一度来たいと思った。4月15日頃がいいだろうと予定を立てていたが天候などで4月19日に伸びてしまった。かって新松田駅からは富士急湘南バスが休日に大野山登山口まで臨時バスが運行されていた。それが富士急モビリティに変わり臨時バスは廃止された。そこで新松田駅からタクシーで大野山登山口手前の都夫良野入口まで行くことにした。
スマホの登山アプリはジオグラフィカを使用している。カシミールで地形図上に登山ルートを作成してそのGPSファイルをスマホに送る。受信メールに添付されたファイルをタップすると自動的にジオグラフィカが起動し地形図上にルートが表示される。ヤマレコやYAMAPも入れているが自分にはこの方法が簡単で合っている。そして念のためルートが載った地形図も印刷して持っていく。
実はこの国土地理院の地形図に誤りがありしょっぱなから道を間違えてしまった。地形図の都夫良野入口からの道は東名高速道路の跨道橋の手前で切れている。都夫良野入口の先にもう一本道がありそれが都夫良野方面に行く道になっている。しかもその道には記念碑の記号がのっている。私は記念碑前を歩きたかったので、タクシーを降りてからその道を進んだ。すると道が塞がって行き止まりのように見えた。そこで200mほど戻って都夫良野入口バス停前から都夫良野方向へと歩いた。
(2025.4.23 地形図の誤りは国土地理院に連絡済。2025.4.25 国土地理院より以下の回答あり。「地理院地図をご利用いただきありがとうございます。 今回情報をお寄せいただきました神奈川県山北町都夫良野の道路表示、また記念碑の位置につきましては、状況を確認し、確認結果に基づいて適切に対応いたします。 この度は有用な情報をご提供いただきありがとうございました。 よろしくお願いいたします。」)
地図記号の記念碑と思われる大正天皇御聖蹟の碑は道路の右側でなく左側(高速道路側)にあった。この道を歩いた登山者のヤマレコ記録にはこの碑の写真が載っていた。この「大正天皇御聖蹟の碑」は不思議な碑であった。ネットで調べた限りではこの大正天皇御聖蹟の碑の情報や写真は一切でてこない。そこでAIに尋ねてみることにした。
AI ChatGTPの回答
神奈川県山北町の都夫良野入口付近にある石碑には、「明治三十三年四月三十日 大正天皇御聖蹟 従二位侯爵 西郷従徳謹書」と刻まれています。この石碑は、明治33年(1900年)4月30日に当時の皇太子であった大正天皇がこの地を訪れたことを記念して建立されたものと考えられます。「御聖蹟」とは、皇族が訪れた場所を示す言葉であり、皇太子の行幸を記念するためにこの石碑が建てられたと推測されます。
石碑の建立者として刻まれている「従二位侯爵 西郷従徳」は、西郷隆盛の弟である西郷従道の子息であり、明治時代の政治家として知られています。彼がこの石碑の建立に関与したことは、当時の政界や皇室との関係を示すものと考えられます。
都夫良野(つぶらの)は、江戸時代には「奥山家道」と呼ばれる街道の一部であり、山北町の歴史的な地域です。この地域には、源頼朝が植えたとされる「頼朝桜」などの史跡も存在し、歴史的な価値が高い場所とされています。
石碑の建立は、皇太子の行幸を記念するとともに、地域の歴史や文化を後世に伝えるためのものであり、現在でもその歴史的意義を感じることができます。
AIの回答は自分で調べた範囲の内容だった。他にこの碑にまつわる疑問は幾つかあるが長くなるのでまたの機会にしたい。
都夫良野入口からつぶらの公園まで標高差210m・距離2.2㎞で1時間ほどの歩きである。緩い上り坂で途中車が数台通った。車道の両側は樹林で日影が多い。ウツギやコゴメウツギの白い花や黄色いヤマブキの花が多い。つぶらの公園に近づくと右手が小高い森のようになり登山者やハイカーがショートカットで土手を乗り越える踏み跡も見られた。左手に地域の集会所があり電波塔が2つ見えてくる。その手前に都夫良野地蔵堂が古びたたたずまいを見せていた。
地蔵堂の道路際に枝垂桜が一本あり終わりかけの花をつけていた。地蔵堂正面入口の格子の中は暗くて見えないが子育てにご利益があるようで乳房を模した絵馬が付けられていた。都夫良野地蔵堂の正確な歴史はわからないが、新編相模国風土記稿(1828年:文政11年)には「地蔵堂 村の南方にあり。堂宇小なりといえども、村民の崇敬厚し。」と記されている。
つぶらの公園を散策する
つぶらの公園入口に到着しやや急な階段を上る。駐車場脇のテーブルベンチは3人連れの女性グループに占領されていたのでトイレ脇で軽い行動食をとる。さくら山に向かって歩き出す。天気はいいが気温と湿度が高く富士山は残念ながら霞んで見える。やはり土曜日でもあり人出もややある。交通が不便なところなので人が多いというほどでもない。急な階段を上りさくら山に登って見たが桜は既に終わっていた。霞んだ富士山と正面に大きな大野山が良く見える。
今日一番のお目当てのつつじ山に向かう。さくら山は標高429m、つつじ山は標高432m、ほぼ同じ高さだが高低差のある通路で結ばれている。つつじ山の斜面の一面にミツバツツジが植えられている。開園から8年目だからかミツバツツジはまだ低く樹高1~2mほどである。ミツバツツジの花は盛りは過ぎているがまだ十分見られる。公園HPには3月~4月上旬と記載されているので少し遅かったようだ。ミツバツツジは階段を登っていく両側に植えられている。登り詰めるとやや広い山頂があり遊具が幾つか置かれている。つつじ山からは相模湾や南足柄市や小田原市など足柄平野が見える。またここには都夫良野地蔵堂の案内板もあった。昔は地蔵堂前から足柄平野が見えたのかも知れない。だが今は地蔵堂前からの眺望はないのでここに置かれているのだろう。
登って来た反対側からつつじ山を下る。こちら側はヤマツツジが多く植えられておりちょうど咲き始めたところだ。ミツバツツジは紫がかったピンク色だが、ヤマツツジは赤みを帯びたオレンジ色である。咲始めでもありミツバツツジとの色の対比がひときわ鮮やかだ。
つつじ山を下り長い階段を下っていくと「東の見晴らし」に着いた。ここからは表丹沢の一部が見られる。眺めを楽しんでから左へ下っていく。
途中に「開運の滝」の分岐を右に見て進む。着いたところが「里の広場」で舗装された丸い広場があり隣接して茶畑があった。大きなマメザクラの木があり付近に東屋があった。風通しが良く見晴らしの良い東屋で昼の休憩をとった。里の広場脇の芝生ではテントが二張りあり子供連れが休憩していた。明るい春の日差しと爽やかな風、緑に囲まれた風景に心癒されるひと時だった。
奥山家道(おくやまがみち)を歩く
つぶらの公園からは奥山家道を歩き川西橋を経て谷峨駅に至る道を歩いた。つぶらの公園から谷峨駅までのコース全体(つぶらの公園内を除く)の標高差-230m・距離4.4㎞で歩行1時間40分ほどであった。このうち、つぶらの公園から長光院前までは標高差-115m・距離2.55㎞で歩行50分ほどで、緩やかな下りだがほとんど平坦に感じた。長光院前からは山道の急な下りが川西橋まで続き、標高差-115m・距離580mで歩行20分程であるがコース中一番の急坂なので滑りやすく注意が必要だった。最後の川西橋と谷峨駅の間に大きな起伏はなかった。
参考:山北つぶらの公園と奥山家道コース
奥山家古道の都夫良野付近
天保年間に編さんされた「新編相模国風土記稿」によると、近世(江戸時代)の山北には、川村山北、川村岸、川村向原の3カ村と、西山家9カ村(皆瀬川、都夫良野、湯触、川西、山市場、神縄、玄倉、世附、中川)、平山、谷峨の村がありました。
この西山家9カ村のうち、玄倉、世附、中川は、西山家の奥、西丹沢の山深いところにあったため、奥山家3カ村とも呼ばれていました。この奥山家へ通じる道であることから、奥山家道と呼ばれました。
※ 西山家は、高松山から丹沢山へ続く尾根の西側にある村を指しています。これの東側にあたる虫沢・宇津茂・柳川・菖蒲など11カ村は東山家と呼ばれていました。
山北町の案内板より
つぶらの公園から歩いて行くと途中に頼朝さくらがあり、大野山への登山口にはトイレが設置されている。
山北町指定天然記念物
都夫良野(つぶらの)の頼朝桜 昭和六十一年八月一日指定
さくらはバラ科の落葉高木で中国大陸、ヒマラヤにもあるが、日本にもっとも種類が多い。古くは花といえば桜を指し、日本国の花である。頼朝桜は天保年間徳川幕府編さんに成る「新編相模国風土記稿」に挿絵と共に載っている。元樹は明治十四年の台風によって倒損し、現在の木は蘖(ひこばえ)の成長したものと伝えられる。樹高十一.六メートル 根廻り二.六メートルである。(この付近は桜平と呼ばれている。)
材質は緻密で家具や船材等に用いられる。園芸品種は非常に多く春、白色または淡紅色の五弁花を開く。郷土の貴重な天然記念物として、指定し保護するものである。
平成元年七月 山北町教育委員会
車はほとんど通らず景色も良く平坦なのでゆったり歩ける。小さな集落が点在するが湯触(ゆぶれ)集落でも数軒それも立派な家が多い。
川西の長光院付近(地形図では大蔵野と出ている)は注意が必要だ。長光院前を左折して50mほど行き直進すると簡易舗装された山道になる。(山道の手前を右折して集落へ入ると須賀神社に行ける)この山道を注意しながら下って行くと途中に馬頭観音が祀られていた。当時は運搬に馬を使っていたため、大切な馬が死ぬとその供養のために馬頭観音を建てたという。
川西橋から工事中の新東名高速道路の橋脚工事が見えた。橋を渡り左方向に行くと途中に小さな「道の駅」があり夏ミカンなどを購入する。もなかアイスは歩きながら食べる。足柄茶直売所もあったので寄ってみる。突き当りの清水橋交差点では信号を向こう側に渡り左折する。安全に配慮された歩道が作られていた。最初の分岐は右に進み、次の分岐は左に進む。田園風景や御殿場線の線路が左下に見えてきて少し歩くと谷峨駅に到着した。
コースタイム 歩行3時間50分(別途休憩60分)距離10㎞ 累積の登り+615m 下り-655m
新松田駅(タクシー¥4200)~都夫良野入口9:22➡(都夫良野地蔵堂)(🥾56分)10:18つぶらの公園(園内散策🥾1時間10分、休憩46分)12:14➡奥山家道(🥾47分)➡13:06長光院前(🥾19分)➡13:25川西橋(🥾15分)➡13:50清水橋(🥾17分)➡14:07谷峨駅
リンクギャラリー
- 2006~2016年252山行
- 2016~2019年38山行
- 十六夜日記
- 季節の風景・植物